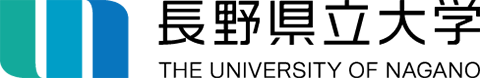教員リレーエッセー第6回『人の心を科学する』
【知覚、認知】
楽しい時間はあっという間に過ぎ去ってしまうのに、苦しい時間や退屈な時間はなかなか終わりませんよね。時計で見れば同じ時間でも、私たちが感じる時間は同じとは限りません。そこで、時計で計測・表示できる時間の長さを「客観的時間」、私たちが感じる時間の長さのことを「知覚時間」と呼び、分けて考えることにします。
一般的に言えば、サービスにとって待ち時間というのはよくないものです。例えば、飲食店でそこそこおいしい料理を食べられたとしても、待ち時間が1時間もあったら、多くの人は今回の食事について不満を感じるでしょう。そこで、サービスを提供する側はいかに待ち時間を短くするか、ということに腐心することになります。テーブルの後片付け、顧客の座席までの案内、注文の仕方の説明、調理、会計などの各段階で極力無駄をなくし、場合によっては多額の費用をかけて機械やシステムを導入することもあります。
このように、作業工程を合理化していくというのは待ち時間を減らす重要な方法ですが、別のアプローチもあります。それは、待ち時間を長く感じさせないようにする工夫です。例えば、「何もしていない時間は、何かしている時間より長く感じる」ということがわかっているので、待合場所の環境を整備し暇つぶしができるような要素をおくことが考えられます。雑誌やマンガ、テレビを設置するというのは昔からある常套手段ですが、今の時代に合わせれば、QRコードから店のアプリに誘導したり、Roblox(3Dゲームの配信サービスで新たなソーシャルプラットフォームとしても浸透し始めている)のエクスペリエンス(Roblox内の企業が提供するゲーム)と連動させたりするような方法があるでしょう。このような方法をとることで、待ち時間そのものは変わっていなくても、待たされていると感じられる時間は減るため、満足度の低下を抑えることができます。
この2つのアプローチの違いは、待ち時間の「時間」の考え方に根差しています。「作業工程を合理化する」というときに考えているのは客観的時間としての待ち時間ですが、「待ち時間を長く感じさせないようにする」というときに考えているのは知覚時間としての待ち時間です。サービス提供者にとって客観的時間が重要なことは言うまでもありませんが、顧客の「知覚時間」というものも同じくらいか、あるいはそれ以上に重要なものであるということを強く意識しておかなければなりません。なぜなら、客観的時間が減った(待ち時間が30分から20分になった)としても、顧客が「待ち時間が減った」と感じなければ意味がないからです。逆に、待ち時間は同じでも、顧客が「あっという間に待ち時間が終わった」と感じれば、待ち時間はさほど問題にはなりません。

待ち時間がわかる信号機は知覚時間を減らすことができます。
ここで取り上げた知覚時間の他にも、知覚品質とか、知覚価値とか、「知覚○○」という言葉がマーケティングにはたくさん出てきます。また、知覚に密接に関連する認知という言葉もマーケティングには頻出します(認知的不協和、認知バイアスなど)。マーケティングは「自然に売れる仕組づくり」などと言われますが、市場(顧客)を対象とした分野なので、顧客の知覚や認知が重要なのは当然のことでしょう。消費者心理とか顧客インサイトなどという言葉がマーケティングの実務の世界で頻発しているのももっともです。マーケティングの中には様々な領域がありますが、その中でも私が専門とする「消費者行動論」という分野(特に購買にかかわる消費者行動を顧客の立場から体系立てた分野)はマーケティング領域の中のまさに一丁目一番地に位置するような分野であり、同時に、心理学(特に社会心理学)の中に含まれる分野であるとも言えるのです。
【心の内面を測る】
心理学は簡単に言えば心のメカニズムを明らかにする学問です。古代ギリシア時代に哲学領域の中で心について議論されるようになってから19世紀前半頃に至るまで、心理学の検証は「内観法」と呼ばれる方法が中心でした。内観法とは、自分の意識や経験を自己観察して、それを(できるだけ)客観的に表し検討するという手法です。心は形がありませんし、心の中は見えませんから、内観法に頼らざるを得なかったのでしょうが、内観法はどこまで行っても主観的な手法であり、カントは「心理学は自然科学にはなれない」とばっさり切り捨てています。
いろいろな学派が共存している中で、20世紀になってから学界の主流となるのはワトソンが提唱した「行動主義」でした。ワトソンは、心理学は客観的科学であるべきと考え、意識(目に見えないもの)ではなく、行動(目に見えるもの)を研究の対象とすべきであると主張しました。例えば、ある広告を見た人がその商品を購入したときに、「(広告を見たときに)どのように感じ、どう考え、なぜその商品を購入したのか」ということについて考えるのはやめて、「広告を見た→購入した」、という行動(結果)のみの関係性に着目したのです。つまり、理由はわからないけれど、広告を見た人は商品を購入することが多い、という客観的事実にフォーカスしたということです。心のメカニズムを明らかにしようとする心理学が、心の内面から離れて、結果として現れる行動のみに焦点を当てる、というのは何だか不思議な感じがしませんか?
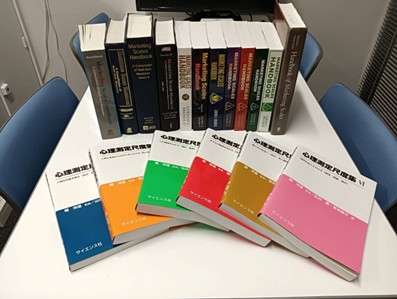
写真は日本で作られた心理学の尺度集とアメリカで作られた
マーケティングの尺度集です。
20世紀後半になると行動主義の限界が明らかになってきて、認知革命が起こります。初心に帰ったというのでしょうか、やはり心の内面に焦点を当てるべきであるという考え方(広義の認知心理学)が主流になっていったのです。認知心理学では心の内面に焦点を当てつつ、しかも科学的でなければならないため、心の内面をいかに測定する(数量化する)か、ということが肝になります。心の内面は形がありませんから、その形のないものにどうやって形(数値)を与えるかということが、非常に困難でもあり、重要でもあり、そして面白くもあるのです。ここでは詳しく述べませんが、定規を使って長さを測ったり、はかりを使って重さを測ったりするのと同じように、「心理尺度」を使って心の内面を測定します。そのため、心理学ではさまざまな概念(心理変数)を測定するための数多くの心理尺度が日々開発され、その妥当性が検証されています。
【情報通信技術の飛躍】
少し話は変わりますが、ここ30年ほどの情報通信技術の成長は目を見張るものがあります。専門家ですら想像できないようなペースで技術革新が進み、当然ながらマーケティングにも非常に大きな影響を及ぼしています。さまざまなビッグデータが手に入るようになり、家庭用のPCとフリーソフトでも非常に高度なデータ分析を素早く行うことができるようになりました。
さらに、そのデータ分析の結果を自動的にマーケティングに活用するようなシステムが実装されていて、しかも、プログラミングの知識がない人がそのようなシステムを生み出せるような環境さえできています。例えば、顧客心理に関する本を読みたいと考え、公共図書館のHPで「顧客心理」というキーワードで検索をかけると、そのキーワードを含むような書籍がもれなくヒットします。しかし、amazonで同じように検索をかけると、そのキーワードを含まないような関連書籍まで含めて検索結果が表示されます。そこでは、同じキーワードで検索をかけた過去の膨大な顧客の閲覧履歴・購買履歴(ビッグデータ)から、関係性が深いと推測される書籍が自動的に推奨されるシステムが作られています。しかも、アカウントを作り、そのアカウントを使って検索・閲覧・購入を繰り返すことで、推奨の精度がどんどん上がっていきます。
【人の心をどう測るのか?そもそも人の心を測る必要はあるのか?】
購買履歴データは行動(結果)のデータであり、仮に多くの人のデータであったとしても、大きな弱点を抱えていると考えられてきました。例えば、ある店舗を利用する顧客の一定期間の利用回数のデータ(購買履歴)から、「ストア・ロイヤルティ(簡単に言えば、あるお店をどれだけ好きかということ)」を知ることができるでしょうか?たくさん利用していたら、その人のストア・ロイヤルティは高いといえるでしょうか?残念ながら、そうは言えなそうです。そのお店をたくさん利用するのは、そのお店がとても好きだからかもしれませんが、家のすぐ近くにあって便利だからかもしれませんし、簡単に利用できるお店がほかにないから仕方なしに利用しているだけかもしれません。よって、購買履歴データを見ても、なぜその人が繰り返しその店舗を利用しているのか?という理由はわからないのです。そうなると、購買履歴データがいくらあっても、その原因を探るためには、結局、心理尺度を使って顧客の心理を測定する必要があるということになります。


アイトラッキングや脳波測定など、脳科学の技術や知見を活かしたニューロマーケティングも進化しています。
しかし、科学技術の進化はとどまるところを知らず、特に近年のAI技術の飛躍により、新たな疑問すら生まれてきてしまいました。それは「本当に(心理尺度を使って)顧客の心理を測定する必要があるのか?」ということです。これまでビッグデータは独立して存在していました(例えば、その人の位置データ(GPSなど)、スーパーの購買履歴、コンビニの購買履歴、インターネットの検索履歴、海外旅行歴などは、それぞれ別々に管理されていました)。しかし、それがスマホや様々なアプリを通じて、すべてのデータが紐づいてしまいました。これによって、ビッグデータは大きく膨れ上がり、情報量も格段に増え、行動の原因すらもかなりの精度で推測できるようになりました。
また、さまざまな計測機器の発達により、脳科学的・認知科学的なアプローチも進化しています。脳波や心拍数といった生体反応や、視線や表情の計測結果などによって、感情や無意識の反応を測定することができるようになってきました。つまり、顧客の心理を直接測定しなくても、行動から心理がつかめるようになってきているということです。さらに、「ビッグデータ→推奨」というシステムはかなり精度が高く、マーケティング施策として非常に優秀であることは、もはや疑いの余地がありません。そうであれば、消費者の行動の理由がわからなくても正確に予測できたり、的確な対処ができたりするならば、少なくとも実務において、行動の理由がわからなくても何も困らないという状況になってしまったのかもしれません。
みなさんは普段の生活の中で、相手の言動から相手の心の内を探ることをほぼ無意識のうちに繰り返していると思います。近い将来、スマホで相手を一定時間撮影したら、その人の心の内を翻訳してくれたり、(人の心の内はわからないけれど)自分との相性をある程度正確に示してくれたりするようなアプリができたら、みなさんはそれを利用するのでしょうか?お互いにカメラのようなものを向けあって、その結果を見ながらコミュニケーションをとるような時代がやってくるとすれば、アナログな私にはずいぶん生きづらい世の中だろうなと思います。

------------------------------------------------------------------------------
【筆者】
中村 陽人 准教授
横浜国立大学大学院国際社会科学研究科博士課程修了 博士(経営学)
専門は消費者行動論・マーケティング
福島大学経済経営学類准教授などを経て現職
【筆者】
中村 陽人 准教授
横浜国立大学大学院国際社会科学研究科博士課程修了 博士(経営学)
専門は消費者行動論・マーケティング
福島大学経済経営学類准教授などを経て現職
【学んだ専門用語】
知覚、認知、マーケティング、消費者行動、内観法、行動主義、心理尺度、ニューロマーケティング、ビッグデータ
【高校生・大学生のためのブックガイド】
エレツ・エイデン、ジャン=バティースト・ミシェル(著)阪本芳久(訳)(2019)『カルチャロミクス ―文化をビッグデータで計測する』草思社
サトウタツヤ・高砂美樹(2022)『流れを読む心理学史 ―世界と日本の心理学[補訂版]』有斐閣
情報文化研究所(山﨑紗紀子・宮代こずゑ・菊池由希子)(著)、高橋昌一郎(監修)(2021)『情報を正しく選択するための認知バイアス事典』フォレスト出版
西内啓(2013)『統計学が最強の学問である ―データ社会を生き抜くための武器と教養』ダイヤモンド社
松尾豊(2015)『人工知能は人間を超えるか ―ディープラーニングの先にあるもの』KADOKAWA/中経出版
知覚、認知、マーケティング、消費者行動、内観法、行動主義、心理尺度、ニューロマーケティング、ビッグデータ
【高校生・大学生のためのブックガイド】
エレツ・エイデン、ジャン=バティースト・ミシェル(著)阪本芳久(訳)(2019)『カルチャロミクス ―文化をビッグデータで計測する』草思社
サトウタツヤ・高砂美樹(2022)『流れを読む心理学史 ―世界と日本の心理学[補訂版]』有斐閣
情報文化研究所(山﨑紗紀子・宮代こずゑ・菊池由希子)(著)、高橋昌一郎(監修)(2021)『情報を正しく選択するための認知バイアス事典』フォレスト出版
西内啓(2013)『統計学が最強の学問である ―データ社会を生き抜くための武器と教養』ダイヤモンド社
松尾豊(2015)『人工知能は人間を超えるか ―ディープラーニングの先にあるもの』KADOKAWA/中経出版